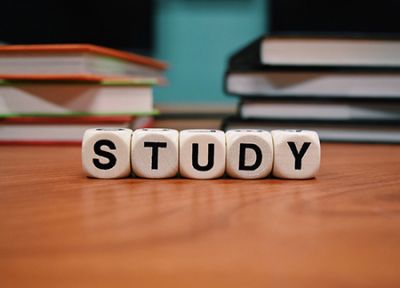日本語学校と言うのは、日本に来る留学生の最初にくぐる門のようなものです。
日本語学校で一度日本語を学んでから、大学・専門学校に進学したり、既に学士を持っていれば就職したりするのが一般的です。
そんな日本語学校ですが、一般的な学校と違って、日本語学校から日本語学校の転校は、なかなか珍しく、そして難しいものです。
ここではその理由に関して、また転校するにはどういった条件をクリアすべきか、見て行きましょう。
1、退学したら即帰国が基本です
日本語学校は、所管行政庁が出入国在留管理庁、いわゆる入管です。
日本語学校は、留学生の在留管理を入管から任されていて、そして、監督されている立場にあります。
もし日本語学校の学生で一定数の失踪者(連絡がつかなくなる学生)が出てしまうと、日本語学校が責任を取らされます。
最悪の場合は、日本語学校としての認可を取消されることもあります。
(もちろん、その前段階で適正校でなくなってしまう)
このような事情のため、日本語学校はまさに自分の命を入管に握られている形です。
ですから、日本語学校は学生が退学しそうな時は、気が気でなくなります。
退学したら、即、帰国して、日本で何か別のことをしてほしくないのが本音です。
何らかの理由で転校するということは、その学校を退学しそうな学生であることが多いわけですから、転校ではなく帰国せよとの指導がなされる場合もあります。
転校元の日本語学校としても、行き先がフラフラしている学生を退学させて、転校させるわけにはいかないのです。
2、受け入れ側の日本語学校もトラブルは嫌い
同じことは受け入れ側の日本語学校にも言えます。
日本語学校を転校するということは、非常にまれであって、往々にしてトラブルを抱えている学生が来る可能性が高いです。
トラブルがあれば、当然、入管に学校が怒られてしまいます。
ですから、そもそもトラブル防止の観点から、「転校の受け入れは、まず認めない」という日本語学校も数多く存在しています。
これは日本語学校の経営判断によるところなので、文句を言えるようなものではありません。
根気よく、転校先の日本語学校を探す必要があるということです。
3、では、どのようなときに日本語学校の転校は認められるか?
まず、元々の出席率が高いことです。
出生率が低いというのは、在留資格「留学」の更新を妨げる大きな要因です。
そして、出席率が低いというのは、アルバイトのし過ぎという問題を抱えている可能性が高くなります。
よって、出席率は最低でも8割以上、通常は9割を超えてないとなりません。
もちろん、出席率が低い他の理由(病気である等)があれば良いのですが、そうであっても転校は難しくなるでしょう。
そして、転校許可証的なものを転校元の日本語学校が出してくれるかどうかです。
ここには、転校理由などが書かれることが一般的ですが、何も書いてない場合もあります。
この転校許可証は、転校先日本語学校が決まってから、転校元日本語学校に発行してもらった方がスムーズでしょう。
「1」に述べた通り、転校元は、先行きが決まっていない留学生は帰国して欲しいのです。
きちんと、この学校に転校できる見込みが高いということが分からなければ、安心することが出来ません。
この転校許可証は、転校先の日本語学校においても必須の書類となります。
というのは、これが入管への重要な疎明資料となるからです。
日本語学校の転校は非常に珍しい手続きであるゆえに、その理由を入管は知りたがります。
よって、転校許可証によって、正規手続きを経た上での転校であったことを証明してあげ、安心させることが必要となるわけです。
4、結局、三方を安心させられるのかということ
結論的に言うと、転校元日本語学校、転校先日本語学校、そして、入管の三者を安心させられるかどうか?というのが重要なポイントです。
そのために、出席率が高いこと、転校許可証がある(きちんとした転校理由なのか)等が必要となります。
日本語学校の転校は出来ない手続きではありませんが、ハードルが高いものです。
まず、受け入れてくれる日本語学校を探して、見つかって相談し、実際に転校できそうなら、元々の日本語学校に転校許可証をもらって、転校するといったプロセスを経なければなりません。
何よりも、これには、転校元と転校先の日本語学校との深いコミュニケーションが絶対的に必須といえるでしょう。
さて、以上、日本語学校から日本語学校への転校がなぜ難しいのかを述べてきました。
何らかの理由で転校しなければならない場合は、それが難しい理由をきちんと把握して、各方面を安心させられる転校を考えて頂ければ幸いです。