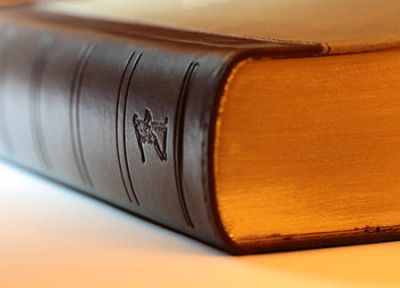ここでは、2019年4月から技能試験の運用を始める予定の「建築・自動車・飲食料品製造」の分野を詳しく見て見ましょう。
技能試験や業務内容、特に各省庁が作る協議会の内容が重要です。
協議会という制度が特定技能の特徴となっています。(これがないのは「建設」だけです)
特定技能ビザの責任の一端を、協議会を所轄している各省へ委譲している形をとっています。
ちなみに、取り上げる分野の順番は私が個人的に気になる、近い分野とさせていただいています。
〇建築
行政書士は建設業の許認可をやっていらっしゃる先生が多いので、たくさんの専門科が注目している分野かもしれまん。
すでに、技能実習で建設業に外国人は入って働いていますが、さらにその門戸を広げようとするものです。
さらに言えば、特定技能2号も建築では準備される予定で、永住申請を念頭に入れた計画を建てることも可能です。
・技能試験
ア、特定技能1号に関するもの
(1)新設の技能試験~建設分野特定技能1号評価試験(仮)
新設の技能試験が開催されます。とりあえず国外において日本語で行われ、必要に応じて国内でも行われます。年1~2回程度で実施される予定となっています。
(2)技能検定3級(リンク:中央職業能力開発協会)
既に日本国内で行われている、建築関係の技能検定です。各都道府県が年間数回行っております。
現在では実務経験6か月が取り払われ、誰でも3級を取得することが出来るようになったようです。
よって、日本にいる留学生などの外国人が、この技能検定を受けて3級を取得すれば特定技能への道が開けます。
そして、運用の穴なのでしょうか?他の国内で行われる新試験では、試験を受けるための条件が課されていましたが、ここにはそのような条件はありません。
つまり、「退学・除籍者、難民申請中、技能実習中、技能実習からの失踪者」でも技能試験に合格し、特定技能へ変更できる可能性は残されているということですが、実務上は非常に厳しい審査が課されるとは予想されます。もしかすれば、難民申請中の方の良い働き口になるかもしれません…。まだ不透明です。
イ、特定技能2号に関するもの
(1)新設の技能試験~建設分野特定技能2号評価試験(仮)
国内において日本語で行われます。年1~2回程度で実施される予定となっています。ただ、平成33年からのスタートの予定です。
(2)技能検定1級(リンク:中央職業能力開発協会)
既に日本国内で行われている技能検定でも、特定技能2号への試験要件をパスできます。ただ、1級は7年以上の実務経験が必要ですから、すでに本国において建築の実務経験がない人が合格するのは無理だと言えます。
・日本語試験
日本語の試験は特定技能1号にしかないようです。特定技能2号は技能試験の中で、業務に関係する専門用語などの能力も判断するのだと考えられます。
ア、特定技能1号に関するもの
(1)新設の日本語試験~日本語能力判定テスト(仮)
新設の日本語能力試験が開催されます。国外だけで行われますが、年6回と非常に頻度が高いことが魅力です。
(2)日本語能力試験(JLPT)N4程度
JLPTという既存の日本語能力試験のレベルがN4でOKです。
ちなみに、N4は英検4級と同じ程度ですので、ほとんど話せない、聞けないという状況であることは予想できます。
だからこそ、日本語の向上のための支援を義務付けているということです。
・人手不足の判断方法
3か月に一度の統計データが提供され、有効求人倍率、労働力調査、建設労働需給調査、建設投資の見通し、人手不足状況の変化の把握が可能な指標を通して、特定技能ビザを持っている外国人の数はコントロールされます。
・従事する業務
建築に必要は業務と、それに付随する業務:作業準備、運搬、片づけなども含まれています。
具体的には、型枠施工、左官、コンクリート圧送、建設機械施工、屋根ふき、鉄筋施工、内装仕上げ、表装です。
・技能実習との関連性
建設業に関わる技能実習2号修了者は、そのまま特定技能ビザで残ることが出来ます。
・協議会なし
特定技能ではすべての分野で協議会が新しく発足することが運用に書かれていますが、建築だけは協議会がありません。
おそらく、建築業は既に強い結びつきが業界全体にあり、協議会の必要性がないからだと考えられます。
〇自動車整備
「自動車整備」は、技能実習で既に外国人が入ってきている分野ですが、新しく特定技能によって受け入れが広げられます。
今までは、自動車整備専門学校を卒業しても、そのまま自動車整備工場へ就職することは出来ませんでしたが、特定技能ビザの出現により、その扉が開くことになります。
・技能試験
(1)新設の技能試験~自動車整備特定技能評価試験(仮)
新設の技能試験が開催されます。国外で、日本語で、年1回程度で実施される予定となっています。
(2)自動車整備士技能検定3級(リンク:日本自動車整備振興会連合会)
建築と同じく既に日本で行われている技能検定が使えます。ただし、3級については、実務が0でも受験できる資格も有ったりしますので、確認が必要です。
自動車整備士専門学校などを卒業していれば、実務なしでも試験が受けられますので、自動車整備士専門学校を卒業してからの進路として新しく考えることが出来ます。
ちなみに、実務経験だけならば、1年以上の実務が必要です。(リンク:国土交通省)
・日本語試験
(1)新設の日本語試験~日本語能力判定テスト(仮)
新設の日本語能力試験が開催されます。国外だけで行われますが、年6回と非常に頻度が高いことが魅力です。
(2)日本語能力試験(JLPT)N4程度
JLPTという既存の日本語能力試験のレベルがN4でOKです。
・人手不足の判断方法
3か月に一度の統計データが提供され、有効求人倍率、業界を通じだ特定技能所属機関などへの調査、協議会による状況把握を通して、特定技能ビザを持っている外国人の数はコントロールされます。
・従事する業務
日常点検整備、定期点検整備、分解整備の業務が行えます。さらに、整備内容の説明、関連部品の販売、清掃などの付随的業務も大乗です。
・技能実習との関連性
自動車整備職種、自動車整備作業の技能実習2号修了者は、そのまま特定技能ビザで残ることが出来ます。
・自動車整備特定技能協議会(仮)
特定技能を就労させる会社は必ずこの協議会に入らなければなりません。そこでの情報共有が基本となります。
受け入れの全体把握、法令順守の啓発、受け入れ状況の把握、転職支援・帰国担保、就業構造・経済情勢の把握と分析などを協力をします。
これは所管が国土交通省です。
また、自動車整備分野は安全に直結する問題なので、自動車整備事業者は、道路運送車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証の取得が求められています。
〇飲食料品製造業
今までは、技能実習によって外国人が働いていましたが、今回、特定技能によってその対象を広げることになります。
飲食料品を製造して売る、小売り業までその範囲は許容されてますので、今まで例えば調理師専門学校をパンやお菓子で卒業しても日本で就職することは出来ませんでした。
その場合は、外国で10年の実務が必要となったのです。しかし、この特定技能によって、その必要は無くなりました。
・技能試験
(1)新設の技能試験~印象区料品製造技能測定試験(仮)
新設の技能試験が開催されます。国内でも、国外でも行われます。現地語で、年10回程度で実施される予定となっています。
なお、開始予定は平成31年10月です。
ただし、国内試験は、退学・除籍者、難民申請中、技能実習中、技能実習からの失踪者は、受けられません。
・日本語試験
(1)新設の日本語試験~日本語能力判定テスト(仮)
新設の日本語能力試験が開催されます。国外だけで行われますが、年6回と非常に頻度が高いことが魅力です。
(2)日本語能力試験(JLPT)N4程度
JLPTという既存の日本語能力試験のレベルがN4でOKです。
・人手不足の判断方法
3か月に一度の統計データが提供され、有効求人倍率、欠員率、欠員数、雇用人員判断(D1)を通して、特定技能ビザを持っている外国人の数はコントロールされます。
・従事する業務
酒類を除く、飲食料品の製造・加工、安全衛生に従事できます。もちろん関連する原料の調達・仕入れ・納品・清掃・事務所の管理なども含まれます。
具体的には、食料品製造、清涼飲料製造、茶・コーヒー製造、製氷、菓子小売り、パン小売り、豆腐・かまぼこ等加工食品小売りです。
よって、町にあるパン屋、お菓子屋、もしくは豆腐屋などに、外国人が就職することのハードルが非常に低くなったということです。
・技能実習との関連性
飲食料品の技能実習2号を終了したものは、そのまま特定技能によって残ることが出来ます。
・食品産業特定技能協議会(仮)
特定技能を就労させる会社は必ずこの協議会に入らなければなりません。そこでの情報共有が基本となります。
受け入れの全体把握、法令順守の啓発、受け入れ状況の把握、人材不足地域の把握と配慮、外国人の保護などを協力をします。
これは所管が農林水産省です。
さらに今回3つの分野を見て見ました。
今まで自動車や調理師の専門学校を卒業しても就職することが出来なかった外国人が就職する道が開けているのが、非常にわかりやすく分かる分野でした。
自動車整備や食料品においては、特定技能2号はないのですが、店長などに抜擢されれば「経営・管理」へ変更をして長く日本で仕事をすることが出来るようになります。